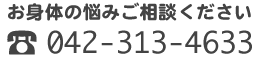【小平市で頭痛にお悩みの方へ】食後の頭痛は「あさば整骨院」で根本改善を
「食後に頭がズキズキ痛む…」
「お腹いっぱい食べた後に決まって頭痛が起こる…」
そんな食後に起こる原因不明の頭痛にお悩みではありませんか?

一般的な緊張型頭痛や片頭痛と異なり、食後の頭痛には消化器と迷走神経の関係が深く関係していることがあります。
小平市の「あさば整骨院」では、食後に起こる頭痛の根本改善を目指しています
当院では、迷走神経と硬膜のつながりに着目した独自のアプローチで、食後に起こる頭痛の根本原因にアプローチします。
頭痛薬に頼らず、再発しにくい身体作りをサポートいたします。
【なぜ食後に頭痛が起こるのか?】
食事のあとに頭痛が起こる原因は、迷走神経と姿勢の変化にあります。
迷走神経とは?
迷走神経は、脳から出て消化器系(胃・腸・肝臓など)をコントロールする神経で、副交感神経の一部です。
頭から首、胸、腹部まで広範囲に伸び、途中で脳を包む膜=硬膜と接触しています。
食後の頭痛が起こるメカニズム
- 食後、胃や腸が重くなり下に引っ張られる
- 姿勢が崩れて猫背になり、首に負担がかかる
- 迷走神経と硬膜が刺激されて頭痛が発生
特に、食べ過ぎ・飲み過ぎは消化器系への負担が大きく、頭痛が悪化しやすくなります。
放っておくと慢性化の危険も…
食後の頭痛を放置すると、迷走神経の働きが鈍くなり、自律神経の乱れや胃腸不調、慢性疲労の原因になります。
また、姿勢が悪いまま固定化されると、慢性頭痛や肩こり、倦怠感など全身の不調にもつながります。
【当院の施術】食後の頭痛を根本から改善する2つのアプローチ
- 迷走神経と硬膜への深部アプローチ
専用の医療機器で、手技では届かない首の深部にある迷走神経と硬膜をケア。神経の働きを正常化し、頭痛の原因を直接改善します。
- 消化器の位置を整える姿勢矯正
背中(胸椎)の可動性を高める施術で、猫背を解消。内臓が正しい位置に戻り、迷走神経への負担を軽減します。
このようなお悩みはありませんか?
- 食後に頭痛が起こりやすい
- 食べ過ぎ・飲み過ぎのあとに頭が痛くなる
- 頭痛薬を飲んでも効かない
- 肩こり・首こりも同時にある
- 猫背が気になる、姿勢が悪い
ひとつでも当てはまる方は、ぜひ小平市の「あさば整骨院」へご相談ください。
【食後の頭痛でお悩みなら、今すぐご相談を】
食後の頭痛は放置せず、早めのケアが大切です。
小平市で頭痛改善をお考えの方は、迷走神経と姿勢に着目した専門施術を提供するあさば整骨院にお任せください。
▶ ご予約は こちらの専用フォーム
▶ お電話でのご予約は 042-313-4633
小平市での頭痛専門施術は、経験豊富な元日本代表トレーナーが直接施術する「あさば整骨院」へ。
あなたの快適な毎日をサポートいたします。
頭痛関連記事:
めまい症や頭痛の予防体操
頭痛のことなら、小平市の整体あさば整骨院へ!普段できる頭痛対策について
頭痛にお悩みの方へ——その原因、首だけではないかもしれません
2025年 3月 7日 9:44 AM
「慢性的な頭痛がつらい」「薬を飲んでも一時的にしか楽にならない」――そんなお悩みをお持ちではありませんか?

実は、多くの頭痛は首の神経が圧迫されることによって引き起こされています。もし、なかなか改善しない頭痛にお困りでしたら、**小平市の「あさば整骨院」**にご相談ください。
なぜ首の治療で頭痛が改善するのか?
私たちの首には重要な神経が集まっており、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、姿勢の悪化により首に負担がかかると、神経が圧迫されて頭痛を引き起こします。特に、胸椎(背中の上部)の動きが悪くなると、首に過剰な負担がかかりやすくなり、神経を圧迫する原因になります。
あさば整骨院では、手技による丁寧な施術に加え、専門の医療機器を使用し、手技だけでは届かない深部にまでアプローチします。これにより、神経の圧迫を解消し、頭痛の根本改善を目指します。
首からくる頭痛の詳しい解説についてはこちらを参考にしてください↓
小平市で頭痛の治療なら、あさば整骨院へ!
頭痛の原因は首だけではありません
首の治療によって多くの頭痛は改善しますが、実は他にも原因が潜んでいる場合があります。特に、水分不足や**蓄膿症(副鼻腔炎)**は見過ごされがちですが、頭痛を引き起こす代表的な原因の一つです。
① 水分不足による頭痛
体内の水分が不足すると、血液がドロドロになり血流が悪化します。脳に必要な酸素や栄養が十分に行き届かなくなり、これが頭痛を引き起こします。特に、脳を保護する「脳脊髄液」の循環にも影響し、圧力の変化が頭痛を誘発することがあります。
また、水分が不足すると筋肉の柔軟性も低下し、首や肩のこりが強くなります。この筋緊張が神経を圧迫し、頭痛を悪化させる要因になるのです。
✅ こまめな水分補給を意識し、1日1.5〜2リットルを目安に摂取することが大切です。
ただし、頭痛対策として日頃から摂取する物はお茶やコーヒーでの水分摂取ではなく、ミネラル水などの純粋な水がおすすめです。
理由① お茶に含まれるカフェインの影響
お茶(特に緑茶や紅茶、ウーロン茶)にはカフェインが含まれており、利尿作用を促進します。これにより体内の水分が排出されやすくなり、脱水症状を引き起こす可能性があります。脱水は血流を悪化させ、脳への酸素供給が不足し、頭痛を引き起こしやすくなります。
※カフェインには一時的に血管を収縮させて頭痛を和らげる作用もありますが、過剰摂取すると逆に「カフェイン離脱性頭痛」を引き起こすこともあるため注意が必要です。
理由② 水分吸収効率の違い
純粋な水は体内にスムーズに吸収され、細胞レベルでの水分補給に適しています。一方でお茶にはタンニンやカフェインといった成分が含まれており、吸収が遅くなりがちです。
③ ミネラル補給にもなる
水(特にミネラルウォーター)は体に必要なカルシウムやマグネシウムを補給できます。これらのミネラル不足は筋肉の緊張を引き起こし、頭痛を悪化させることがあります。
頭痛対策のための水分摂取のポイント
- 1日1.5〜2リットルを目安に、こまめに水を飲む。
- お茶を飲む場合は、カフェインの少ない麦茶やルイボスティーがおすすめ。
- 起床後・入浴後・運動後は特に意識して水分補給をする。
頭痛予防には、カフェインを控えつつ、純粋な水をこまめに摂取することが効果的ですよ。
あくまでこれは日頃の頭痛予防に対して効果的であり、前述したように激しい頭痛症状が出ている時にはカフェイン摂取は有効です。
② 蓄膿症(副鼻腔炎)による頭痛
蓄膿症とは、鼻の奥にある副鼻腔に膿が溜まり、炎症を起こしている状態です。この炎症によって鼻周辺の圧力が高まり、特に目の周りやおでこにズーンと重く感じる頭痛が現れます。
さらに、副鼻腔の腫れが三叉神経(顔の感覚を司る神経)を刺激し、頭全体に痛みを広げることもあります。頭を下げると痛みが悪化する場合は、蓄膿症が関係している可能性が高いです。
✅ 慢性的な鼻詰まりや鼻水がある方は、早めの治療(医師の指導)をおすすめします。
頭痛を放っておくと危険です
「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、頭痛が慢性化し、吐き気やめまい、集中力の低下を引き起こすことがあります。特に、首の神経圧迫による頭痛は、悪化すると日常生活に支障をきたすことも。
早期の対応が何より重要です。つらい頭痛から解放され、快適な毎日を取り戻しませんか?
あさば整骨院にご相談ください
小平市の「あさば整骨院」では、頭痛の原因を見極め、あなたに合った適切な施術を提供しています。
首の神経圧迫からくる頭痛はもちろん、水分不足や蓄膿症が関係する頭痛についても、お一人おひとりの症状に合わせた対応を行います。
つらい頭痛でお悩みの方は、ぜひ一度ご来院ください。あなたの健康をサポートし、快適な日常生活を取り戻すお手伝いをいたします。
2025年 3月 6日 4:59 PM
「膝が痛くて正座ができない…」「深く膝を曲げると引っかかる感じがする…」
このような膝の痛みでお悩みではありませんか?
膝の痛みは日常生活に大きな支障をきたし、放置すると症状が悪化することもあります。特に、正座ができない方は膝関節周辺の筋肉や組織が硬くなり、スムーズな動きが妨げられている可能性があります。
膝が深く曲げられない原因とは?

膝を深く曲げる動作には、膝関節周囲の複雑な組織が関係しています。以下の要因が膝の動きを制限し、正座を困難にしていることが多くあります。
-
膝蓋下脂肪体(しつがいかしぼうたい)と膝蓋上嚢(しつがいじょうのう)の硬さ
膝を深く曲げるときに働く、膝蓋下脂肪体や膝蓋上嚢が硬くなることで、膝のスムーズな曲げ伸ばしが阻害されます。特に正座の際に違和感や痛みを感じる原因になります。
-
膝蓋骨(膝のお皿)の動きの悪化
本来、膝を曲げると膝蓋骨は下方向に移動しますが、組織の硬さによってその動きが制限され、深く膝を曲げられなくなります。
-
下腿(膝から下)の回旋制限
通常、膝を深く曲げる際には脛骨(けいこつ)がわずかに内旋(内側に回る動き)します。この内旋ができなくなると、骨同士がぶつかり、痛みや引っかかりが生じることがあります。
これらの状態を放置すると、変形性膝関節症に移行する可能性もあります。
正座ができない膝痛症状と半月板への影響
正座ができない状態が進行すると、膝関節のクッションである半月板が損傷することがあります。半月板は膝のスムーズな動きを助け、衝撃を吸収する重要な役割を担っています。
-
内側半月板と半腱様筋(はんけんようきん)
内側半月板は、太ももの裏にある半腱様筋とつながっており、膝を曲げる際に半月板を引っ張り、関節内の引っかかり(ロッキング)を防いでいます。この連携が乱れると、膝がスムーズに曲がらず、痛みや違和感が発生します。
-
外側半月板と膝窩筋(しっかきん)
外側半月板は膝窩筋とつながっており、同様に膝を深く曲げる際に半月板を引っ張り、関節の動きを助けています。硬さや筋肉の緊張によってこの機能が低下すると、膝の屈曲時に強い痛みを引き起こすことがあります。
これらの半月板が損傷すると、膝の痛みの他にも「引っかかる感じ」や「カクカクとした不安定感」を感じやすくなるばかりか、症状が進行すると日常生活にも大きな影響を与えます。
あさば整骨院の治療法—正座できる膝を目指して
小平市にあるあさば整骨院では、膝の痛みに対して次のようなアプローチで施術を行っています。
-
深層の筋肉・組織をほぐす
手技では届かない深部の筋肉や組織を、医療機器を使用して丁寧に緩めます。膝蓋下脂肪体や膝蓋上嚢、膝蓋骨周囲の硬さを解消し、膝のスムーズな動きを取り戻します。
-
膝関節を安定させる筋肉を強化
膝を支える筋肉を鍛え、関節への負担を軽減します。膝の安定性を高めることで、痛みの再発を防ぎます。
-
正座に必要な関節の動きを改善
十分な柔軟性を確保した後、下腿の内旋を促しながら膝関節を動かすことで、正座ができる状態へと導きます。
当院では、医療機器を多く使用しているため、手技だけでは難しい深層の硬さにもアプローチでき、早期の改善を目指します。
手術が必要な場合もご相談ください
骨の変形が進行し、関節の隙間が完全に消失している場合には、手術が必要となることもあります。こうした場合には、専門の医師と連携し、最適な対応をお勧めいたします。
膝の痛みで正座ができない方は、あさば整骨院へ!
膝の痛みは放置すると悪化しやすく、将来的に手術が必要になるケースも少なくありません。早めのケアで、痛みのない快適な生活を取り戻しましょう。
「膝が痛くて正座ができない…」とお悩みの方は、ぜひ小平市の整体「あさば整骨院」にご来院ください。
あなたの膝の状態に合わせた施術で、正座ができるようサポートいたします。
ご予約・ご相談はお電話またはWebからお気軽にどうぞ。
小平市で膝の痛みにお悩みなら、あさば整骨院が解決のお手伝いをいたします。
2025年 3月 5日 8:56 AM